
コラム
Column
人材育成
2025年02月17日(月)

部下を育成することは、マネージャーの重要なミッションのひとつです。
部下の成長を促したいと思いつつも、人材育成の専門知識を持たない現場マネージャーは、何をどうしたら部下が育つのか分からないとお悩みの方も多いようです。
一方で、人事部門も現場主導でもっと効果的に人材育成を進めてほしいというジレンマを抱えているケースも散見されます。
当記事では、部下育成の意義や育成を行ううえで必須で押さえておくべき5つのポイントを紹介します。部下育成で失敗するパターンも紹介するので、現在部下育成に課題を感じている方も、これから部下育成をする方も参考にしてください。
業種や職種にかかわらず、部下育成は企業にとっての重要課題のひとつです。
特に少子高齢化が進む昨今においては、外部からの人材採用よりも既存社員である部下を育成する重要性は増しているでしょう。
ここからは、部下を育成する意義をあらためて考えてみます。
業績を上げていくためには、組織内で安定的に部下育成を行う必要があります。
昨今はマネージャーのプレイヤー化が進んでいるため、つい目先の業績に気を取られて、部下育成を後回しにして自ら業務を担う人も少なくはありません。
部下育成を怠ってしまうと、マネージャーが何らかの理由でいなくなった時に、意思決定が滞り、現場が混乱するリスクがあります。その結果、組織として安定的に業績が上げにくくなってしまいます。一方、部下が成長すれば、現場で速やかな判断が出来るなど組織力が底上げされ、業績低迷を防ぐことにつながります。
このように、中長期の目線で考えると、組織業績を向上させるために部下育成は必要不可欠です。
マネージャーが部下育成を行うことで、チームの一体感や団結力の向上に効果を発揮します。
上司が部下の業務をサポートすることで、上下の協力関係が築かれます。その過程で、自分の経験だけでなく同僚のナレッジ共有をすることで、横のつながりも芽生えやすいでしょう。
特にメンバーが単独で動く傾向がある営業組織で、チームの一体感を醸成するために部下育成を戦略的に活用できると、組織力の向上につながりやすくなります。
ゆくゆくはマネジメント不在の際も、チームメンバー同士でナレッジ共有がなされるなど、マネジメント負荷の低減効果も期待できるでしょう。
部下育成をすることで、社員一人ひとりの市場価値が向上する効果もあります。
ついつい自部署のみの観点で、部下を見てしまいがちですが、部下は会社の人的資本です。部下育成をしてメンバーの市場価値が上がれば、企業価値の向上にもつながります。
上司が部下を育成するなかでスキルが向上することはもちろんですが、その過程で自社の理念やビジョン・文化といった部分も継承されていきます。
また、部下には部下のキャリアプランがあり、よいマネジメントは部下のキャリア目標を踏まえたうえで、今の仕事に意味づけをすることができます。
部下が成長して、キャリアアップしていくことを支援する姿勢を忘れないようにしましょう。
ここからは多くの企業で取り入れやすい部下育成の手法を紹介していきます。
「OFF-JT」とは「Off-The-Job Training」の略称です。
部下が、実際の仕事現場を離れて、外部講師が主催する研修やセミナーに参加するなどが代表的なものです。昨今ではe-ラーニングでのオンライン講座の受講も、OFF-JTの主流の手法となりつつあります。
日常業務では得られにくいスキルや技術を習得できる、集中して学べる、といった点がOFF-JTのメリットです。
一方で、外部への支払いコストが生じる、研修参加中は業務に穴が空いてしまう、といったところがデメリットでしょう。
また、現場を通じた部下育成として、「在籍出向(在籍型出向) 」も昨今では注目の手法です。
自社に籍を残したまま、自社とはまったく異なる環境の他社で経験を積むことができるのが、在籍出向の特長です。
いずれは自社に戻るため、期間限定で他社での経験を通じて部下育成をしたいケースにはおすすめの手法です。
ボルテックスが提供する在籍型出向サービス「Vターンシップ」は、全国約4.7万社のネットワークから貴社のご要望に沿った最適な出向先をご提案します。
人材業界出身の経験豊富なキャリアアドバイザーが、送出企業様、受入企業様双方に情報を共有しながらサポートするため、出向期間終了まで安心してサービスをご利用いただけます。

出向期間中、これらのサポート対応は追加料金なくご利用頂けるのも魅力のひとつです。
「OJT」とは「On-The-Job Training」の略称です。
具体的には、上司や先輩が指導者としてつきそいながら、現場業務を通して部下を育成する手法です。
OJTは、多くの企業で取り入れられている育成手法で、現場で活躍できる即戦力メンバーを育てるには、効率的な施策といえるでしょう。
しかし、上司や先輩にそれなりの負荷が発生するのが、OJTの注意ポイントです。
昨今では「1on1ミーティング」など、マネジメントの負荷が軽減する、ライトな面談を通じて部下育成をする手法もあります。
「自己啓発」とは、部下が自主的に行う能力開発やスキルアップのことです。Self Developmentを略して「SD」と呼ばれることもあります。
具体的には、書籍を読んだり、社外講座に通ったりと手段は多岐にわたります。自己啓発にかかる経費を会社が一部負担する教育補助制度を導入する企業も増えています。
自己啓発は、社員側の自主性が高いため、従業員満足度の向上につながる点がメリットです。その一方で、企業に強制力がないため、コストに見合った成果を得られない懸念もあります。
部下を育成するためには、意識しておきたいポイントがあります。
ここからは、部下育成を効果的に行うために押さえておくべきポイントを5つ紹介します。
育成内容を部下の気持ちに届けるためには、部下の価値観を知る必要があります。
部下には部下の数だけの価値観があります。部下のAさんには効果を発揮した指導方法が、別の部下であるBさんには機能しないという事態も起こりえるでしょう。
たとえば「Aさんは細かい指導方法を好む」が「Bさんはある程度自分に任せられることを好む」などが、価値観の違いです。
現代ではダイバーシティの言葉に代表されるような、多様化の時代です。
部下の価値観を把握することは、育成の効果を上げるための前提として重要なポイントです。
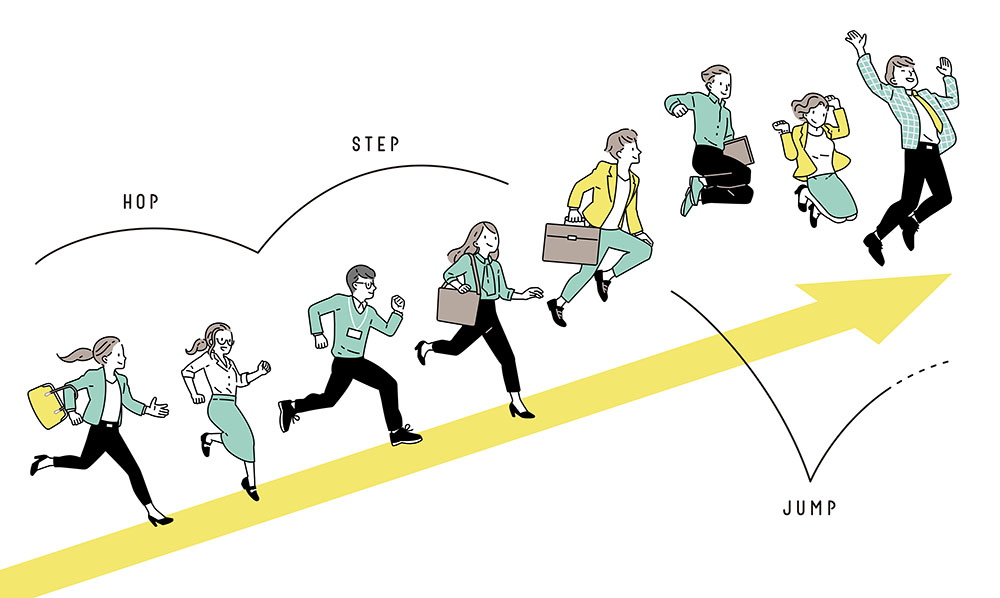
部下育成をするにあたっては、一人ひとりに合わせた目標を設定してください。
できれば部下と一緒に目標設定し、ゴールを共有することが望ましいでしょう。
育成したい内容が、本人も「鍛えたい」と思っている内容とすり合っていれば、育成のスピードや質が上がりやすい傾向にあるからです。
目標設定のポイントは、「高すぎず・低すぎず」のゴールを目指すことです。目標が高すぎたり低すぎたりする場合、育成施策に取り組む前からモチベーションを下げてしまう恐れがあります。
もちろん、本人の意向によっては「今期はチャレンジングな成長をしたい」と思っているなら、あえて高い目標を設定することもありえます。
いずれにしても、育成の到達点や到達プロセスは部下によって異なるため、一人ひとりに合わせた目標設定の必要があるでしょう。
失敗やつまずく経験は、成長につながる大切な機会といえます。失敗したことを活かして、次の成長を促すことは、部下育成の重要なポイントです。
失敗を感情的に怒ったり咎めたりすると、部下が萎縮してしまい、なかなかチャレンジできない風土にもつながりかねません。
ただし失敗そのものを良しとしてはいけません。「なぜ失敗したのか」「次に失敗しないように、何をあらかじめ対策するか」という振り返りを部下とともに行い、次につなげるように心がけてください。
このような育成を通じて、部下が自律的に経験を振り返る習慣も身につくことも期待できるでしょう。
部下の育成においては、仕事を任せて、主体性をはぐくむことが非常に大切です。
もちろん、仕事を任せられる状態になるまでは、丁寧な指導も必要となるでしょう。徐々に任す範囲を増やしていき、部下が自ら考えて仕事を行える状態を目指します。
このように、部下に実行プロセスで主体的な判断の権限や責任を付与していくことを「エンパワーメント」といいます。
集中して主体性を鍛えたい場合は、前述した「在籍出向」も効果的です。現在の職場とは異なる他社の環境に身を置くことで、自ら考え・動く力が身につきやすいでしょう。
部下育成の観点では、育成を施す側も一緒に成長する意識も重要です。
たとえば新任管理職であれば、任される部下は数名かもしれません。しかしポジションが上がれば上がるほど、管轄する部下の人数は増えていきます。人数だけでなく、「年上部下」など、育成の難易度が上がるケースに遭遇することもあるでしょう。
さらに大きな責任を持つ管理職になるためには、自分自身も成長サイクルに入ることが大切です。
部下から育成へのフィードバックをもらいながら、さらに自分の育成スキルを磨くことを心がけましょう。
このように部下の成長のサイクルに自分を入れることで、2つの成長サイクルが同時に回るような状態となり、さらに組織力が向上していきます。
部下育成がうまくいっていないケースで散見される、3つのNGパターンを紹介します。
育成と思い込んで、部下に対して一方的な指示しかしないのは、避けるべき行動です。
指示とは「こうしなさい」「こうすべきだ」といった断定的なもので、初期の導入教育時やトラブルや緊急時の業務対応などに用いられるものです。
しかし、本来の仕事は臨機応変に対応しなければいけないことが多いため、部下自らが考えて行動することが大切になります。したがって、部下育成の観点では「こうしなさい」の前に「どうしたらいいと思う?」と部下に考えさせることが望ましいでしょう。
簡単に答えを与えてしまうと、部下の成長する機会が失われます。そこを理解できる上司でなければ、部下育成を成功させることは難しいです。
仕事の結果にしか着目をしていないと、効果的な部下育成から遠のいてしまいます。
育成のポイントは結果ではなく、プロセスに現れるものです。
たとえ「受注できなかった」という残念な結果であっても、プロセスには「資料作成のレベルがあがった」「アポイントの数が増えた」など、成長の兆しはあるはずです。そのフィードバックをすることで、部下も次の成長や成果にモチベーションを上げてくれるでしょう。
逆に「受注した」という望ましい結果が出たとしても、本人は特にプロセスでは何もしておらず、単なる“ラッキー受注”だったケースもありえます。
そのようなときもプロセスでもっと工夫すべきといった指導をし、次の行動改善を促してください。
育成は部下本人の気持ちに届いて、初めて効果を発揮します。そのため、本人の心情や気持ちを無視した育成は、狙いどおりの効果が期待できません。
本人が今何を課題に感じているか、不安に感じているかをあらかじめ理解し、その状況に沿った育成を進めてください。
日常的なコミュニケーションでも、部下の心情理解は重要です。
部下育成に長けている人は「落ち込んでいるときは、励ましを」「緊張しているときは、リラックスを」など、相手の感情に応じたやり取りを心がける特長があります。
最後に、部下を育成するうえで必要となるスキルについて言及します。
ここでは、アメリカの経営学者であるロバート・L・カッツが提唱した「カッツモデル」を紹介します。管理者(マネージャー)のスキルについての研究や調査を行い、3つのスキルが必要であることを発表したのがカッツモデルです。
具体的に3つのスキルについて解説をしていきます。
テクニカルスキルは、担当業務を遂行するために必要となるスキルのことです。
部下を育成するためには、テクニカルスキルがないと上司として部下育成をすることは難しいでしょう。特に専門性が高い業務では、部下にお手本を見せるのは育成面において必要となるからです。
また部下の業務が適切に行われているか、仮に間違っているならどの点を修正すべきなのかを把握し、伝える必要があります。その観点でもテクニカルスキルは重要です。
ヒューマンスキルとは、業務に関係する他者との関係性を構築するスキルです。
部下育成の観点では、部下との信頼関係を構築し、育成成果を最大化させるよう働きかけをする力ともいえるでしょう。
ヒューマンスキルは多岐にわたりますが、最たるものは「コミュニケーションスキル」です。特にコミュニケーションでは、部下の価値観を把握するための質問や、部下のビジョンを引き出すための関係を築く力が求められます。
部下育成に限らず、他者と信頼関係を構築しながら成果を創出するためには、必須のスキルといえるでしょう。
コンセプチュアルスキルは「全体を俯瞰し、把握する力」のことです。
企画段階から具体的な将来像を描き、実効性が高い解決策を導くスキルです。
たとえば、伝わりやすい方針を描いたり、市場環境を分析して計画を立てたり、問題を解決する能力全般がコンセプチュアルスキルには含まれます。
上位職になればなるほど、目の前の業務のみならず、他部門や世の中の動向など多くの要素を踏まえて考える必要があります。部下育成も同様で、業務経験を俯瞰・抽象化して伝えることが必要になるのです。
部下育成を真剣に行うためには、ある程度の中長期目線が必要です。
現在の経営トップやマネージャーたちは、いずれ定年退職などの理由でいなくなることも考慮しなくてはならないからです。
その後、会社を牽引できる人材を育成できている企業は、一時的な社内の混乱があっても、中長期的には成長し続けるでしょう。一方、人材が育っていないと企業は、安定的な企業成長は見込みにくくなります。
当記事で紹介した部下育成のポイントを参考に、ぜひ企業成長目線での部下育成に取り組んでいただければ幸いです。